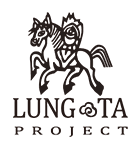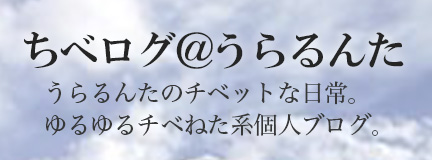チベットNOW@ルンタ
ダラムサラ通信 by 中原一博
2014年9月7日
ウーセル・ブログ「蛮人の舌」
北京在住のチベット人作家ウーセルさんは、8月15日付けブログの中で、自身が中学卒業後四川省の州都成都で学んだが故に、漢語ばかりが流暢になりチベット語を正確に発音することができなくなったと話される。また、中国人が「兎の肉も食べることができない蛮人」と呼ぶチベット人の文化を自ら進んで捨て、中国文化に「同化」し自我を失ってしまった自分を後に悲しみ、ラサに帰ることで辛く長い時間をかけ悲しい経験を経て再びチベット人としてのアイデンティティーを取り戻すことができたと語られる。
原文:蛮子的舌头
翻訳:M女史
絵 ウーセル: ニュー・ヨーク・タイムズ記事原文:蛮人の舌より。蛮人の舌
ツェリン・ウーセル
1981年初秋、日益しに漢化の進むチベット東部の小さな街・康定(チベット語でダルツェド)で中学を卒業した私はちょうど、成都にある西南民族学院予科部(高校に相当する)のチベット族学生募集にぶつかった。この予科部は1985年に始まったのだと思うが、同化の加速を目的とし、北京や上海など様々な都市で創建されたチベットクラス、チベット中学の前身に当たり、実験的な性質を備えたものだ。当然、政府側の言い分はすべて「チベットの人才培養を幇助する」というものだった。
決して両親に励まされてのことではなく、純粋に個人の願望によって私は予科に出願した。反抗期のただなかにあった私は両親に束縛されることを望まなかったうえ、成都が新鮮な事物に充ち満ちた大都市であると感じていて、中国とチベットにどのような違いがあるのかも意識していなかったし、自分の郷里や、属する文化と次第に遠のいてゆくことになるなどとは予想もしなかったのだ。
軍服を着た父が私を成都まで送ってくれた。私たちは座席の固い長距離バスに乗り、高い高い二郎山(チベット語では何といっただろう?)を越え、その後、窓の外の風景は青々とした竹、大きな野菜畑やたわわに実った果物になった。私たちがバスを降りた時、まず私に見えたものは路傍のレストランの前に置かれたたらいの中、積み上げられた寂しげな兎の頭が人を誘う香りを撒き散らしているところであった。私はいっときぽかんとなり、即座に思い出したのは兎の肉を食べると口唇裂になるというチベットの民間の言い伝え、眼前にはあの高山を穿ち谷を縦横無尽に走る道路の上、チベット語で「リボン」と発音する兎の突然死ぬところが現れた。
真っ向からやって来たものの多くが、大きく違っていた。飲食、外見、言葉……紅焼鱔魚(タウナギの醤油煮)を食べ始め、麻辣兎頭(兎の頭の辛味煮)を食べ、蛙の肉を食べた。これらを食べれば禁忌に背くことになるのは分かっていたが、食べないのはすなわち迷信深い“蛮人”なのだということはもっとよく分かっていた。成都人は“蛮人”という言葉を好んで口にするようだったが、兎の頭さえ食べられなければそれだけでもう、瓜兮兮の“蛮人”になるのであった(瓜兮兮の意味するところは大馬鹿者である)……成都は湿気の多い盆地で、私と同族の学友たちは髪の毛がひどくカールするのに驚いた。一般の人はこうした“天然パーマ”を少数民族の特徴と見なしていた。そこで私たちは毎朝長くカールした髪を櫛で激しく梳き、カールした髪を直毛にしようとしたが、結局は髪を切って耳のところまでの短髪となり、髪はカールしたままだったが、パーマをかけたように見え、成都の通りにいる中年女性みたいだった。
民族学院に設けられた予科は閉鎖的な“小学校”で、私たちはキャンパスの一角に据えられた二つの大教室で授業を受けた。私たちが成都の中学生と接触することはなく、同年齢の彼らが毎日何を学んでいるかまったく知らなかったが、恐らく私たちと同じだったろう、結局私たちと彼らの教科書は完全に同じで、他にもう一冊チベット語やイ語の教科書が出されることなどあり得なかった。私の学友の多数はチベット人で、あとはイ族だったが、チベット語とイ語が話せる者は何人もおらず、時間の推移に従って、みな流暢な成都方言になっていった。後になって、ラサの親戚は私の舌が「手術された舌」だと形容した。顫動音、巻舌音、歯齦音(歯茎音)など何種類かの伝統的なチベット語の音が、出せなくはなかったが出せばおかしな音になり、チベット語の「ラサ」という言葉すら正しく発音できなくなっていたのだ。
大学に通った経験は更に、取り換えられる経験だった。西南民族学院には全体で三十余りのそれぞれ呼称を持つ少数民族がおり、私たちを多民族の環境で生活しているかのようにさせていたが、これらの民族の歴史や文化はまったく理解しておらず、知っていたのは幾つかの民族の祭日にその民族風味の料理が一度だけ出るとか、或いは篝火を囲んで酒を飲み歌ったり踊ったりするとか、或いは洗面器で互いに水をかけ合いタイ族の“水かけ祭”をやってみることぐらいだった。多民族の特色は私に自分が“チベット族”という状態の中に置かれているのだと常に感じさせはしたが、ネイティヴとしてのいかなる教育も受けたことはない。
私は秦始皇帝の長城改修は立て板に水でもポタラ宮がいかに築かれたかを語れなかった。唐詩宋詞はすらすらと暗誦してもダライ・ラマ六世の詩歌を読めなかった。私は赤色中国の若干名の革命烈士は熟知していたが、1959年のラサ蜂起におけるチベット人自身の英雄については理解していなかった……幸い私はラサを忘れてはいなかった。そこが私の出生の地であり、四歳の時父母についてチベット東部に移ったのだが、それ以来ラサに対する郷愁を深く抱いていた。1990年春になって、私は大学卒業二年目にしてついに戻り、政府主宰のチベット文学雑誌社で編集を担当したのだ。
しかし、ラサに到着して最初の見聞は私を驚かせた。子供の時の記憶ははっきりせず、私の父が当時撮影した写真の中からラサのぼんやりとした印象を残せているだけだったのだ、独特の風格を備えた美を有しているというような。現実には実弾入りの銃を持った軍人が全域に満ち、一台また一台装甲車がゴロゴロと大通りを踏み敷いていたのだが、これは1989年3月、僧侶、尼僧や平民を含む多くのチベット人たちが街頭に出て、1959年に中国政府がチベット人の反抗を鎮圧したことに抗議したためで、それで今回、北京はラサに対して一年七ヶ月もの長きにわたる軍事戒厳令を敷いていたのだ。
両足はラサの地面に立ちながら、私は一種の深い孤独感をおぼえていたが、疑う余地もない、それは手術された舌の引き起こしたものだった。私は、自分が完全で標準的なチベット語をほぼ話せず、口から出てくるのは却って四川訛りの北京語なのだと気付いた。だが、私の母語はもともと中国語などではまったくなく、私の問題は、私の母語が成長過程の中で取り換えられてしまったことにあるに過ぎないのだ。私はこれは私が麻辣兎頭を食べたからで、禁忌を犯した人間は外貌まで変わってしまうのではないかと疑いさえした。
二十年ぶりにラサに戻った私は実は自我を失った私だった。そして私の自我に対する探求、拒絶、受容……最後に今の立ち位置からチベットの物語を述べるようになったが、本当に長い、長い時間を費やした。だが万事万物の形成にはすべて原因があるのであって、私が別の人間に取り換えられたのにも原因があるのだ、まさしく「鳥が石の上に落ちるのも、純粋に天の巡り合わせである」というチベットの諺のように。幸運だったのは、私は心臓まではすり替えられなかったことだ。
今もなお私にとって忘れ難いのは初めてトゥルナン寺に行った経験である。それはそこから重大な転機が生じることを意味し、更には強大な電流のように、異化に遭った私に立て続けに命中した。あれはある黄昏のこと、チベット人の伝統を保っている親戚に連れられて寺院に行った。なぜだか分からないが、私が進むうちに説明のつかない涙が湧き出してきた。笑みをたたえた釈迦牟尼の仏像に出会うと、むせび泣きが漏れ、内心でこう言う声が聞こえた。「お前はついに帰ってきたのだ。」しかし私はすぐに痛苦をおぼえた。そばにいた僧侶がチベット語で感嘆するのが聞こえたからだ。「このギャモ(漢人の女の子)はなんて可哀想なんだろう」
筆者プロフィール

中原 一博
NAKAHARA Kazuhiro
1952年、広島県呉市生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。建築家。大学在学中、インド北部ラダック地方のチベット様式建築を研究したことがきっかけになり、インド・ダラムサラのチベット亡命政府より建築設計を依頼される。1985年よりダラムサラ在住。これまでに手掛けた建築は、亡命政府国際関係省、TCV難民学校ホール(1,500人収容)、チベット伝統工芸センターノルブリンカといった代表作のほか、小中学校、寄宿舎、寺、ストゥーパなど多数。(写真:野田雅也撮影)