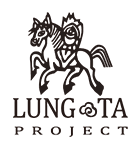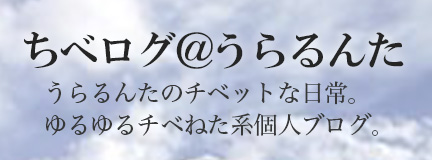チベットNOW@ルンタ
ダラムサラ通信 by 中原一博
2010年12月7日
ドルジェーエフ/在日モンゴル人作家ダシ・ドノロブ「モンゴルとチベット かつての出来事1」
 最近日本でもダラムサラの旧友棚瀬慈朗氏が書かれた「ダライラマの外交官ドルジーエフ /チベット仏教世界の20世紀 」http://amzn.to/eBkxeM とかが出版され。
最近日本でもダラムサラの旧友棚瀬慈朗氏が書かれた「ダライラマの外交官ドルジーエフ /チベット仏教世界の20世紀 」http://amzn.to/eBkxeM とかが出版され。
急に「チベットの外交官ドルジェーエフ」の名がチベットファンの間にささやかれるようになったようだ。
で、このドルジェーエフについて、在日モンゴル人作家ダシ・ドノロブさんが最近中国語でコラムを発表された。
これを、うらるんたさんが翻訳して下さっているのを見つけたので、本人承諾の上、ここにそれを転載させて頂く。
連載もののようだが、今回は特に後半で「中国のチベット人への漢語強要政策批判」が展開されている。
なお、ウーセルさんも同じものを12月5日のブログに掲載されている。
http://woeser.middle-way.net/2010/12/blog-post_05.html
以下、12月7日付、うらるんたさんのブログより。
http://lung-ta.cocolog-nifty.com/lungta/2010/12/101206.html
—————————————————————-
モンゴルとチベット かつての出来事1(訳)
在日モンゴル人作家ダシ・ドノロブさんが「民主中国」に寄稿したコラムです。
先日の「チベットの歴史と文化学習会」でテーマになっていたドルジーエフについてモンゴル人の視点から触れておられたのが興味深かったのでざっと訳してみました。チベットでのいわゆる「双語教育」についても、経験者の視点、隣人の視点、ある意味“双語教育”が成功し漢語を自由自在に使いこなすお立場からの視点、そして日本というさらなる「異民族の言語の海」に飛び込まれた視点からの指摘をもっとうかがってみたいと思いました。
原文はこちら(「民主中国」�甼希东日布:蒙藏往事(一)) 。
http://minzhuzhongguo.org/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=17814
表題は(1)となっており、文章も「続く」となっていて、何回かの連載となるようです。
———————————————————–
蒙藏往事(一)(モンゴルとチベット かつての出来事 その1)
ダシ・ドノロブ(モンゴル人作家)
2010年10月21日、たまたま次のようなニュースを目にした。
ダラムサラ発の「国際西藏郵報」(The Tibet Post International)で、記事は「『1913年蒙藏条約』国際シンポジウムがモンゴルの首都ウランバートルで開かれ、モンゴル、インド、米国、韓国、ロシア、カナダ、台湾、オランダ、ドイツからの専門家が参加した」というもの。報道によると、「今回のシンポジウムは、モンゴル内外の学識者27人で組織する研究団体を含め、1913年にモンゴルとチベット両国で交わされた友好同盟条約と締結の合法性をテーマに討論する。この条約を締結したことにより、モンゴルとチベットは相互を独立国家として承認したことを宣言した」という。
その記事で、私はある人を思い出した――ダライ・ラマ13世の外交官、ブリヤートモンゴル人のドルジーエフである。多くのブリヤートモンゴル人同様、彼の名前も非常に特徴的で、前半部分の「ドルジー」はチベット語の単語「ドルジェ」からの借語、後半部分の「エフ」はロシア語の語尾である。このドルジーエフこそが、1913年に「蒙藏条約」を調印したチベット側代表者なのだ。
一編の新聞記事に、私の好奇心が刺激された。このブリヤートモンゴル人はどのようにしてチベット政府の代表となったのだろうか? この条約が締結された当時の国際情勢はどのような状況だったのだろうか? まるまる100年の間、モンゴル人とチベット人――この、同じ宗教を信仰する二つの民族はどのような歴史の過程を歩んできたのだろうか。
まもなく、私は図書館で1冊の本を探し当てた。書名は「ダライラマの外交官ドルジーエフ チベット仏教世界の20世紀」。1ページ目を開いた私は、次のような描写に読み至った。
初めて日本に到着したドルジーエフは、日記にチベット語を用いて次のように記している。「今日は長崎という港町に到着した。ここは仏教寺院がとても多いが、参拝する者は少ない。人口が非常に多く、国土は非常に狭い。ここの人たちは自らの民族意識と自尊心が非常に高い。聞くところによると、彼らはどこに行っても心の中で自分たちの国家のことを考えているという。しかし、この国家はほとんど戦乱がなく、国内は非常に安定している。おそらく、このように内政が長期安定することにより、国家は大国として発展し、国際社会で名声を博しているのであろう」
(訳注:今原著を人に貸し出し中なので原文参照できず二重翻訳になってます。後で原文に戻します)
この段落を読み終えて、私は、ドルジーエフのこの旅行は外交目的であったことを推測した。あの列強が横行する時代に、チベットやモンゴルのような弱小民族が自身の民族の利益のために列強の各大国と渡り合わなければならず、縦横に交錯するそれぞれの覇権主義勢力のパワーバランスを縫って、民族が生き延びるための隙間をさぐらなければならなかったのだ。日本とロシアのはざまのモンゴル人と、イギリスとロシアのはざまのチベット人は、宗主国である清王朝の絶体絶命の窮地に直面して、何を捨て、何を選びとるべきだったのだろうか。
当時、漢人の革命党人員(訳注:辛亥革命)はとっくに「駆逐韃虜、回復中華(打倒満州族、中華復権)」という民族主義のスローガンを叫び、 「鉄血十八星国旗」をデザインし、「漢地18省に限った」独立運動を始めていた。(いわゆる鉄血十八星国旗とは、赤・黄・黒3色を組み合わせ、赤地と9角の黒色が「血」と「鉄」を象徴し、革命が必ず鉄血主義=武器と兵力=によるものであることを象徴する。黒い9角の星は、歴史書「禹貢」に記載のある古代の9州=冀、�芽、青、徐、揚、荊、豫、�碇、雍=を表し、事実上、モンゴル、チベット、ウイグルなどの「韃虜=ダッタン人の呼称が変化した蔑称、“異民族野郎”」の居住地域は含まれていなかった。黒い9角の星形の内外両側にある計18個の丸い黄色い星は漢民族の内地18省を表したもの。18個の星の黄金色は、満州人の立てた清朝「韃虜」と対立する漢民族すなわち「炎黄子孫」=炎帝と黄帝の子孫=を示している)
「鉄血十八星国旗」をデザインし、「漢地18省に限った」独立運動を始めていた。(いわゆる鉄血十八星国旗とは、赤・黄・黒3色を組み合わせ、赤地と9角の黒色が「血」と「鉄」を象徴し、革命が必ず鉄血主義=武器と兵力=によるものであることを象徴する。黒い9角の星は、歴史書「禹貢」に記載のある古代の9州=冀、�芽、青、徐、揚、荊、豫、�碇、雍=を表し、事実上、モンゴル、チベット、ウイグルなどの「韃虜=ダッタン人の呼称が変化した蔑称、“異民族野郎”」の居住地域は含まれていなかった。黒い9角の星形の内外両側にある計18個の丸い黄色い星は漢民族の内地18省を表したもの。18個の星の黄金色は、満州人の立てた清朝「韃虜」と対立する漢民族すなわち「炎黄子孫」=炎帝と黄帝の子孫=を示している)
当時の革命党員の「野心」は決して大きなものではなく、ただ「満州人ら異民族を追い払い中華を復権させる」、すなわち内地18省の漢人の主権を取り戻し、チベット(青海)、モンゴル(内外蒙)、新疆ウイグル及び満州(東三省)の主権はすべて漢人にはあずかり知らないものであった。これが、(辛亥革命の)革命党員が当初主張した民族主義(ナショナリズム)だったのである。
武昌起義(辛亥革命の幕開けとなる武昌の兵士たちの反乱:1911年10月10日)から1912年10月まで、鉄血十八星旗は中華民国の国旗と定められていた。当然、崩壊寸前の清王朝に直面して、漢人の革命党員のみが自民族を守ろうと奮起したのではない。モンゴル人、チベット人の精鋭たちも座して死を待つことなく、漢人同様に立ち上がり、自らの民族国家を樹立しようと力を尽くし始めた。あるいはもしかしたら、ドルジーエフも、ロシアのチベット独立支持を求めてペテルスブルグに向かい、孫文は当時の満州を譲ることを条件に日本に対して漢地18省が独立することへの支援を取りつけ、清王朝の立場から見れば「国外の帝国主義勢力と結託し国家を分裂させる」挙動を取っていたのかもしれない。
しかし、誰がどのように歴史を解釈しようとも、歴史的事実そのものが書き換えられはしない。少なくとも、我々はまず、この100年の間に結局は何が起きたかという事実を理解しなければならないのだ。
このようにして、はるかロシアに旅立ったドルジーエフが、私にこの100年間のモンゴルとチベット両民族の歴史と現状を振りかえらせる契機となった。
1.漢人の悲しみとチベット人の怒り
2010年10月21日の「国際西藏郵報」(The Tibet Post International)で私はドルジーエフを思い出した。しかし、当時の丸一カ月間、チベットに関する主要なニュースは、アムド(青海省)で起きたいわゆる「双語教育(バイリンガル教育)」に抗議するデモの報道に占められていて、これはこれでまた私に、言語教育と民族文化の継承の危機の問題を思い起こさせるものだった。
劉力は仲睦まじい3人家族で、来日して既に10年になろうとしている。彼が学んだ専攻は引く手あまたの分野で、現在はあるソフトウェア開発企業の役員となり、高い給料を受け取り、東京でも高収入家庭に属している。
去年、劉力の両親は初めて親族訪問で来日して三世代が一堂に会し、本来であれば皆で大いに喜びあうはずだった。しかし、おばあさんは孫を見つめて悲しみに耐えられず涙を流し、おじいさんも傍らでため息をつくばかりだった。劉力の両親をこれほどまでに悲しませたのは、孫の「言語の問題」だった。劉力の息子は日本語しか理解できず、中国語は一言も話せず、祖父母と孫の世代は意思疎通の方法がなくなっていたのだった。
あるいは、老夫妻の悲しみにはもっと多層的なものがあったかもしれない。まず、親子の情からみれば、祖父と孫の2世代の交流に言葉の壁があることは既に十分に彼らを気落ちさせるに足ることであろう。それ以外にも、我々はさらに彼らの心を傷つける理由があったことは軽視できない。このように自分の跡継ぎの世代が民族の言葉や文化を失う姿を目の当たりにするのは、ある種の心理的ショックとしては言葉の壁以上に強烈なものかもしれない。彼らの可愛い孫が、漢民族文化を伝える核心となる支柱―中国語―を失っているとは。まだましなことに、漢民族の全体からみれば、すべての漢民族の子供が同じ問題に直面しているわけではない。もしそうであれば、この民族そのものが滅亡の危機に瀕していることになってしまうのだ。後になって劉力は私にこう言った。両親は常に彼らに帰国するよう勧めるんだ、漢人の自分たちの場所に戻ってこい、家族を大切にして後の世代に言葉と文化を伝えてくれ、と。もちろん妻は断固として反対し、息子が既に東京の生活環境になじんでいることも考慮に入れた劉力は、帰国する考えは毛頭ないという。仕方のないことではある。彼は職業上の更なる飛躍のため、自らの意志で日本の「先進的民族」の言語の海の中に入ることを選んだ人間なのだ。
では、我々は老夫婦の悲しみをどのように理解すべきなのだろうか。理屈からいえば、彼らの子孫1人当たりの生活水準は、中国のような発展途上国家の10倍に当たる。息子はコンピューター技師で、人がうらやむほどの安定した高収入を得ており、心身ともに物質的に満足できる消費生活を送っている。
ここで、イギリスの著名な経済学者コーリン・グラント・クラークが提唱した幸福の定義を見てみよう。クラークは初めてGNP(国民総生産)の概念を用いて一つの国家経済の生活の質を評価した。これはいわゆる「個人の幸福」を解釈する方法で、クラークはまず「持続的に生活必需品を購入できるに十分な現金収入があることが必須条件」として、我々が幸福な生活のためには基本的な衣食住と交通手段が必要であることを理解させた。続いて、クラークは「(生活必需品に加えて)趣味や娯楽への欲求を満たすに十分な財産が必要」と分析した。これは例えば読書や知的好奇心を満たすためのインターネット接続などの精神文化生活といえるだろう。ただし同時に、コーリン・グラント・クラークは特に次のことを強調している。「伝統や伝統を継承するための欲望は必ず満足させなければならない。つまり祖先が伝統的に満たしてきた欲望は、将来的に子孫末裔に伝えられるべきものである」。彼はこれを「個々人の幸福として無視できない重要な構成部分」と認識している。
劉力の両親にとって、自分の孫の身に起きたことはまさにこの最後の一項目が満たされないことに当たり、悲しみと幸福欠乏感の現任に当てはまっている。見たところ、民族文化をつなぎとめるか喪失するかは、人類の個人の幸福指数に直接に影響を及ぼすといえそうだ。
2010年月、アムド(青海省)で、幸福だと感じることを脅かされた人たちが、街頭へ出て怒りを表した。彼らは劉力と異なり、異民族の都市へ移住したなどということはなく、個人の成功のために自らなにか「先進民族」の言語の海に飛び込んだというわけでもなかった。彼らが自分たちのふるさとで自民族の言葉の危機に直面しているのは、彼ら自身が選んだ行動の結果ではなく、政府の政策によって引き起こされたものであった。彼らはなにもせず、誰も招きいれず、誰も誘発しなかったのに、政府は突然文章を発表し、彼らの学校内の大部分のカリキュラムでチベット語で授業を受けることを停止するよう求めた。
少し考えてみよう。もし北京のある漢族学校で、「国語(中国語)」と「英語」以外のすべての教科で、教科書をチベット語に変え、チベット語で学ぶことになったら、学生や先生たちはどのようなショックを受けるだろうか? ある人はこう反論するかもしれない。「中国語は『国語』であり、チベット語はそうではない」。よろしい、我々はこの2種類の言語が法律的地位において確実に不平等であることを認めるわけだ。我々はチベット語は中国語に比べて一段低い存在であると認めることになる。これが現状である。
もっとも、チベット語がなぜ国語ではないのかといえばこれには二つの政治的原因がある。第一に、チベットは主権独立国家ではなく、自分たちの民族言語を法的に政府の言語にするすべがない。第二に、チベットは「自治地区」でさえなく、カナダのケベック州のようにフランス語を政府言語のひとつとして設定するすべさえもない。
中国政府は我々がこのように言語の法的地位の不平等さについて論じることさえ面白く思わず、我々がこの種の不公平は漢民族のこの国家内の人口比例からして権力を一手に握ることに発するものだ、と論じることも許されない。当然、我々が言語に関する不平等な政策の合理性について分析することも認めていない。
彼らは大いに自信たっぷりに中国語がその国土で独尊的な優先権を持つと主張し、悠然と語る。中国はカナダではなく、シンガポールではなく、スイスでもない。中国が、漢語(中国語)以外のいかなる民族の言語にも漢語と同等の法的地位を与えることがないのは中国の特徴である。甚だしくは、彼らは「中国が広く宣伝している民族平等は『民族の言語の地位の平等』とは違う」と放言する。このような言語の不平等政策が学校教育分野で体現されたのがすなわち「バイリンガル教育」なのである。
チベットでの「バイリンガル教育」は元来、チベット人自治地域のすべての小中学校でチベット語と漢語2種類の言語を同時に教えることをいうものだと思う。理屈からいえば、チベット地域の漢族学校ではチベット語を教える義務はないはずだが、非常に不合理な事情のもと、現在は反対に、チベット人学校で元からあるチベット語の授業を減らし、あからさまな文化的絶滅政策が横行している。一種の「非我族类,虽远必诛(同族でなければ殺しても)」式の、狭隘で残忍な自民族中心主義を体現したものだ。まったく、同じ先祖に生まれなかったからといって何をあわてるのだろうか? まさか、あなた方の民族が強勢を誇っているからといって、ほかの民族の言語や文化を手段を選ばず根絶やしにしてもかまわないなどと考えているのだろうか? ナチスドイツが行った人種的特徴上の大量虐殺と比較しても、文化的意味合いでの民族根絶政策はさらに偽善性と残忍さを備え、柔らかい刀でじわじわとなぶり殺すようなものである。
いわゆる「バイリンガル教育」政策の背後から、ひそかに隠れて囁く、怖ろしい呪詛の声を耳にするのは簡単だ。「チベット人どもを滅ぼせ!」。その声ははっきりと聞き取れる、凶悪な呪いだ。(続く)
筆者プロフィール

中原 一博
NAKAHARA Kazuhiro
1952年、広島県呉市生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。建築家。大学在学中、インド北部ラダック地方のチベット様式建築を研究したことがきっかけになり、インド・ダラムサラのチベット亡命政府より建築設計を依頼される。1985年よりダラムサラ在住。これまでに手掛けた建築は、亡命政府国際関係省、TCV難民学校ホール(1,500人収容)、チベット伝統工芸センターノルブリンカといった代表作のほか、小中学校、寄宿舎、寺、ストゥーパなど多数。(写真:野田雅也撮影)