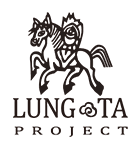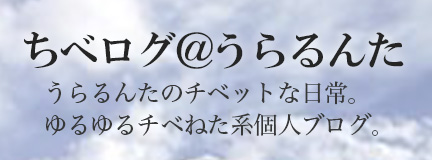チベットNOW@ルンタ
ダラムサラ通信 by 中原一博
2009年8月29日
ジャミヤン・ノルブ氏「独立チベットの論拠をめぐって」・Y女史訳
明日(日本はもう今日)はいよいよ選挙、日本にも「CHANGE」の波が来ようとしているようです。
日本のチェンジはともかく、早く中国に来てほしいものです。
 選挙と言えば、Y女史のブログに静岡まで行って、投票日前の牧野聖修候補に会ってきた話が写真とともにレポートされています。
選挙と言えば、Y女史のブログに静岡まで行って、投票日前の牧野聖修候補に会ってきた話が写真とともにレポートされています。
以下でご覧ください。
http://epea.exblod2009-08g.jp/-28
そのY女史は最近ジャミヤン・ノルブ氏から直接送られてきたという彼の「チベット独立論」を翻訳されました。
http://epea.exblog.jp/i18/
Yさん御苦労さまでした。
以下、少々長いですが、このブログでもこっそり紹介させて頂きます。
『ランゼン: 独立チベットの論拠をめぐって』 ジャムヤン・ノルブ
“RANGZEN: The Case for Independent Tibet” by Jamyang Norbu
(訳注・ 本稿は、ジャムヤン・ノルブ氏が当初、2006年に発表した論考を昨年、2008年版としてブログに再録した原稿について、日本語訳の可能性を伺ったところ、さらに推敲を加えた最新版をジャムヤン氏より直接送付いただき、翻訳する運びとなったものです。)
*************************************
■ 2008 Introduction
2008年版 序論
チベットにおいて、古(いにしえ)の山と雪獅子の旗を掲げることは、見つかればその場で銃殺されかねない「分離主義派」の違法行為とされている。にもかかわらず、今年(2008年)一連の歴史的な蜂起において、数百にのぼるあまたの国旗が、チベット全土において挑戦的に翻った。いわば、抗議者達による「ランゼン」を求める声――すなわち、独立を求める声が、響き渡っているかのように。
チベットの人々がランゼン、すなわち独立を求めているという事実に、疑いの余地はない。その他の要求、すなわち「ダライ・ラマ法王の帰還」を求める希望すらも、それは真の意味において、独立を宣言する行為にほかならない。なぜなら、法王は他の何物にもまして、自由なチベット国家という存在の不朽の象徴だからである。まさしく今、チベット全土にわたって、ウ・ツァン、カム、アムドにおいて、人々は独立の夢、ダライ・ラマ法王のチベットへの帰還という夢を、しっかりと握りしめている――中国による残虐で容赦のない軍事弾圧に直面しながら。
ラサから戻ってきたオーストラリア人ジャーナリストは語る。「私は……街が中国軍の重圧の下で軋みをあげているのを目撃した。」 2008年11月8日付の詳細なレポートで、彼は次のように述べている。「チベットの首都ラサ旧市街の裏通りでは今週、世界の目から隠れて不気味な軍事作戦が展開されている。夜の帳が降りるころ、数百もの中国軍事部隊が暴徒鎮圧用の盾とアサルトライフルを手にして、この反抗精神に満ちた街に散開した。彼らは街角に歩哨を立て、パトロール隊を放った。いかなる抗議の兆しも見逃すまいと、ラサ・チベット人街の通りを夜通し歩き回るのだ。陽が昇っても、兵士達はいなくなるわけではなく、新しい部隊と入れ替わる。そうして昼間のラサの軍の締め付けにおいては、さらにもう一つ、身も凍るような措置が加えられる――この市街で最も神聖な場所であるジョカン寺の屋上に、狙撃手達が配置されるのだ。彼らは、その下の(ジョカン寺の周囲を取り囲む広場である)バルコルにたどり着いた数百ものチベット人巡礼者達に向けて、銃を構えている」
このエッセイは、世界に広がるチベット人に対して、私達の理念「ランゼン」の歴史的、政治的、および倫理的な正当性を今いちど検討してもらうべく促すために、ここに再録している。この理念を胸に、チベット域内にいる私達の兄弟姉妹達は勇敢に立ち向かい、投獄され拷問され、処刑され続けている。そしてこのエッセイは、私達共通の夢を実現するにあたって彼らと一体になるために、私達の担う責任や献身について、再び新たにすることをも意図している。
■ 2006 Introduction
2006年版 序論
人間の歴史には、ごく稀でありながらも決定的な瞬間がある。その時、圧倒的で一見して永久に続きそうな専制状態、その無慈悲な構造の表面に、迫りくる崩壊の最初の小さなひび割れがあらわれる――そして、長い間抑圧されてきた人々の心、虐げられてきた国々の中に、希望のかすかな揺らめきが湧きおこる。ベルリンの壁の崩壊は、東欧や中欧、中央アジアの一部において、そうした時の移り変わりの前触れを告げるものだった。
チベットの人々にとっても、そうした変化はすぐ間近に迫っているのかもしれない。中国の経済成長は、中国社会を分裂させかねないような、膨大で解決しがたい数々の問題や紛争を生み出している。中国固有の官僚腐敗、絶望に駆られた貧しい農民の蜂起、大規模な労働騒擾、苛烈な宗教弾圧、刻々と拡がる経済格差、(黙示録的な規模で拡大しつつある)環境破壊、独立した法廷の不在、そしてほとんど存在すらしない市民社会――こうした要因によって2005年、(中国政府の公式報告によると)8万3000を超えるデモや騒乱、数多くの暴力事件が中国全土に広がった。今年(2006年)もあと4ヶ月を残すところとなったが、そうした社会の騒乱について報告されている数は、すでに10万件以上にのぼっている。
近年、中国共産党指導部のとある上級党員らが、2008年の北京五輪に際して数百、数千もの外国人訪問者や世界の報道陣が押し寄せた時に起こるかもしれない事態について懸念を表明している、と伝えられている。中国情勢のオブザーバー達によると、そうした状況はチベットやウイグルの独立支持活動家達に、また、疎外され抑圧を受けてきた中国人達にも、世界の衆目の前に抗議を展開する格好の機会を与えることになる。
アジアの歴史におけるかくも重大な岐路にあって、チベット人は自らの独立を求める闘いに関わり合うことに対して、躊躇したり弱気になったりしないことが、致命的に重要である。また、チベットの友人達や支援者達、また世界全体においても、チベット人やチベット文明の存続のためにはランゼンが絶対に必要であることを理解していただき、独立した祖国を求めるという主張がいかに著しく道理にかなっており、節度ある正当な要求であるかについて、正しく認識してもらうことが、きわめて肝心だ。
■ Origins of Tibetan National Identity
(先が長いので、この一節は省略します。あしからずご了承ください)
■ Legitimacy of Tibetan Independence
チベット独立の正当性
独立国家としての地位を求める私達の主張がいかに長年にわたる理にかなった要求であるか、私達チベット人自身が理解することが、絶対に必要である。この世界における多くの国家は一面において、ほとんどが歴史の産物だ。アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアは、本当の意味で、自国の起源をチベットのように国土に依っているわけではない。クウェート、ヨルダン、シンガポール、そしていくつかのアフリカの国々は、西洋の植民地政策の産物、または植民地支配の残骸から形成されたともいえる。最近では、かつてのソビエト社会主義連邦の崩壊から、ベラルーシ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンといった国々が誕生した。これらは、かつては国家として存在したことのなかった国々である。
世界からの国際的な注目度を考慮すると、パレスチナという国家もまた存在したことがなかった、と指摘する向きもあるかもしれない。歴史的に存在していたのはオスマン帝国における一地方、州(vilayet)であり、それは後にイギリス保護領となった。イラクもまた、第一次大戦後にイギリスが、敗北したオスマン帝国の3つの州、モスル、バグダッド、バスラをとりまとめて作り上げた国家である。今日のかの国における解決しがたい暴力的な分裂、民族および部族間の派閥の存在は、この連邦の根拠の乏しさをあらわにしている。
本稿は、チベットが上記に挙げた国々や領土よりも国家として存在する権利がある、と論じるためのものではなく(結局のところ、自分自身の人生・生活スタイルを決める権利は万人が生まれ持つ基本的な権利である)、国家としてのチベットの立場が世界の他の国々(以上ではないとしても、他国)と同様に、正当で筋の通ったものである、という事実を強調するために書かれている。私達が国際連盟や国際連合に加入してこなかったこと、あるいは、いくつかの大国が中国との交易関係を危険にさらしたないたくないばかりにチベットを国家として認めてこなかったこと――こうした事柄は、国家としてのチベットの正当性を少しも損なうものではない。
中国との貿易は、過去二世紀の間イギリスとアメリカが独立国家としてのチベットを支援するどころか認めることさえ拒否してきた、事実上最大の理由である。1930年代、まさに「チベットにおけるイギリス政策の立役者」であり、チベットに関する権威であったサー・チャールズ・ベルは、次のように認めている。
「イギリスとアメリカ、そしておそらくほとんどのヨーロッパ各国は、チベットを中国支配下の存在とみなしている……そのうえ、中国との貿易の莫大な潜在性については、常に論じられてきた。記憶している限りでも、50年前にもそれについて語られていたが、その後の50年間でそうした莫大な潜在性は現実にはならなかった。潜在的なものは、潜在的でしかない。しかし、諸外国は中国の交易から十分に利益を得たいと望み、その目的のために中国に気に入られようと試みてきた。だが、中国における商業利権を増やしたいがためにチベットを売らなければならないというのは、嘆かわしいことである」
チベットがその歴史を通じて、外国勢に征服されていた時期があるという事実、また、幾人かのチベット人統治者は政治上の支配力を獲得するために外国の軍事力に頼っていたという事実も、自由な国家としてのチベットの正当性に、何の違いももたらさない。18世紀と19世紀、チベットの政治力・軍事力が著しく衰え、満州(*1)の支配が国中に及んだ時でさえ、チベット文明の独自性やその民族的・国家的アイデンティティは、(チベット長官としては名門の出身の満州人とモンゴル人しか選出せず、決して中国人を任命しなかった)満州自身によってのみならず、アジア全域の人々によって広く認められていた。実際に、満州のチベットとの関係は(満州の「外務省」、外地統治を担当していた中央官庁の二つの「局」のうちの一つだった)「理藩院」(Li Fan Yuan)によって司られていた。この局は、満州宮廷とモンゴル大公、チベット、東トルキスタン(新彊)、ロシアとの関係を担当していた。
**********************
訳注 *1 「満州」: Manchu
中国清朝を指す。
ジャムヤン氏の英文でQin DynastyではなくManchuの語が使われているため、その表記に合わせました。
**********************
チベット、とりわけ首都ラサは、ロシアのブリヤート人やカルムィク人、数百万ものモンゴル人によって、文化と信仰の中心地と見なされていた。1878年、ロシアの探検家プルジェワルスキーは地理学協会および陸軍省に、次のように書かれた覚書を送っている。
「……彼はラサを、アジアにおけるローマとして描いた。その精神的な影響力は、セイロンから日本にいたるまで、250万人に及んでいる。ロシア外交にとって最重要の対象である」
世界において、一時でも他国の支配下に入ったことのない国など、おそらく存在しない。もし継続した揺ぎない独立の歴史を証明しなければ国家として認められないとしたら、国連加盟国の中で独立国家を名乗れる国はほとんどなく、あるとしてもごく僅かであろう。1960年、チベットに関する国連での議論においてアイルランド使節団が指名された時、もし国連総会に出席していた各国が過去にどの国からも支配されたことがないことを証明しなければならなかったとしたら、ほとんどの国はその国連総会に参加しえなかっただろう。
イギリスはほぼ四百年もの間、ローマ帝国の一部だった。ロシアは二世紀以上にわたって蒙古の支配下にあり、また言うまでもなく、アメリカはイギリスの植民地として始まった。中国自身も蒙古と満州の両方に支配されていた時代があり、チベットとの戦争においては繰り返し敗退を喫している。763年には一時、チベットが長安を占領した時期もあった。しかも、忘れてはならないのは、20世紀の前半には中国の領土の相当部分が日本の統治下に入っていた時期もあったことである。
■ Inside Tibet Now チベット内部は今
世界中でおそらく、チベットのようにスターリン主義の政治体制下に統治されている地域は(おそらく北朝鮮を除いて)ないであろう。とりわけラサは、最も厳格な状態にある。この厳しい現実は、西洋からの旅行者、そしてナイーブな(うぶでだまされやすい)亡命チベット人の訪問者からもほとんど見過ごされてきた。彼らは中国の無節操な全体主義システムについてはあまりに無知なまま、中国の「素晴らしき新しき資本主義社会」のスケールに感銘を受け、時としてその歯車に引き込まれてしまう。
現在チベットを訪れる人々は(いわゆるチベット「専門家」を含めて)、日常で出会う人々が中国による統治に対してあからさまに抗議の意を示さない様子を見て、チベット人は現状に満足していると結論付け、中国共産主義の支配下にある生活の実態を相変わらず考慮に入れそこねてしまう。バツラフ・ハベルは、強圧的な圧政の下で暮らす人々が、知的・社会的・政治的行為に関して保たざるをえない「二重人格」について、克明に記述している。単刀直入にいえば、「誤った」意見を持つ国民を罰するといった国家においては、単に訪問者が人々の真の気持ちを見過ごしがちな傾向に陥ってしまうのみならず、その国家体制自体もおそらく、そうした国民の真意の実態について把握しにくくなるだろう。
中国当局は1979年、ダライ・ラマ法王特使がラサに到着した際に受けた圧倒的な感情に満ちた大歓迎を目の当たりにして、唖然としていた。当局は、ランゼンを支持しているチベット人は「ほんの一握り」しかいないと、ある程度まで実際に信じていたようだった。問題の深刻さゆえに、当局が基本的な秩序の再建をはるかに超えて抑圧的な方策をとらざるをえなくなるまでは。
ディスコやカラオケバー、売春宿、ナイトクラブ、ホテルなど、コンクリートの建物のけばけばしく安っぽい正面玄関の内側で、中国政府のぞっとするほどあからさまな数々のキャンペーン、「容赦なき抑圧(1988)」「強打(1966、2001、2004)」「死に至る闘争(2006)」運動が、厳格に推進されている。人民解放軍(jiefangjun)、武装警察(wujing)、強制労働収容所(laogaidui)、国家精神棟(ankang)、公安(gongan)、国家公安部(anquan or guoanbu)、そして「相互監視」システム(danwei)といった制度が、(労働)単位(work unit)、「愛国再教育」チーム、近隣保安監視(neighborhood security watch)、そして絶えず存在している密告者達によって遂行される――こうした制度すべてが、自由にあけすけに機能している。それらは、独立状態にある法廷、自由な報道、市民団体、独立した監視機構、倫理的・宗教的な意見といったものとはかけ離れており、しかも世界の報道機関も常駐せず、何者にも妨げられずに存在している。世界中で最悪の統治が行われている国々であっても、中国指導部がチベットで何の責任も問われることなく遂行している暴虐な専制独裁政治を回避しないまでも、(上記のような)制度が何らかの形で、いくばくかは存在しているものだ。
2006年5月、チベット自治区 共産党書記の张庆黎(Zhan Qingli)は、ダライ・ラマ法王に対する「死にいたる闘争(Fight to the Death)」運動を発表した。チベット人は、政府の最も低い役職から上級職員に至るまで、いかなる宗教儀式への参加も許されず、寺院や僧院に行くことも禁止された。以前は、党員だけが宗教を放棄するよう強要されていた。僧院における愛国教育運動は拡大された。ラサとその周辺地域にいるチベット人職員は、ダライ・ラマ法王を批判する文章を書くように強制されている。下級職員は5000語の非難文でよかったが、上級職員は10000語の文章を書かなければならない。引退している職員さえも免れることはできない。
チベット域内では、数十年にわたる魂を破壊するような共産主義の教化や、世界でも最も冷酷で衰えることのない圧政のシステムを経て、チベット人の「ランゼン」独立への希望はまだ、断固として圧殺されることを拒んでいる。現時点では大規模なデモは可能ではないとしても、勇気ある個人、尼僧、僧侶、そして一般の人々が、数か月、数年の間、禁じられているチベット国旗を掲げ、反中国のポスターを貼り、公衆の前でランゼンを叫び続けてきた。2003年10月2日、ニツォ僧院の20歳の僧侶ニマ・ダクパは繰り返し拷問を受けて獄中で死亡した。彼はチベットの独立を求めるポスターを貼ったことにより「分離主義」活動の罪を問われ、9年間の刑に服している最中だった。2006年9月3日、人々で込み合うラサのバルコルで、23歳の僧侶が一人でチベットの独立を求める短いデモを行った。数分で彼は中国保安要員に拘引されていった。このような、数百もの似たようなケースにおいて注目すべき点は、スローガンとして叫ばれていた合い言葉が例外なく「ランゼン」であったことだ。
■ Why Rangzen is Absolutely Essential
なぜランゼンが絶対に必要なのか
いくつかの国々は他の国家や帝国の配下にあってもどうにか生き延びているどころか、外国の統治によって利益を得ているような場合もあるだろう。最も顕著な例はいうまでもなく、イギリス統治下の香港だった。けれども、たとえ熱心な中国の支援者であっても、中国によるチベット支配は成功したと思しき点が見当たらないどころか、イギリスによる香港支配と比べたら人道的にも自由度においてもほど遠いということを認めざるをえないだろう。
とはいえ、比較的良質な外国による支配であっても、一見したところ、先住民の文化や意識、気力に弊害をもたらしている兆候がある。オーストラリアやカナダは豊かな経済に恵まれ、(少なくとも今日では)先住民を含む自国民の権利を護るための様々な民主制度の発達した先進国だ。けれども、こうした国々では多くの先住民達が道徳的に堕落し、貧困と病にさいなまれ、アルコール中毒の犠牲となり、絶望に瀕している。こうした状況は、チベット域内で起こりつつある現象と不気味なほど酷似している。
外国による統治下で、多少なりとも自尊心を保ちながら生きのびる唯一の方法は、圧政を強いる権力に対して常に対抗・挑戦し、最終的には自由を獲得する、という希望を保ち続けることであるように思われる。もし暴君に対して抵抗すれば、征服者側から敬意すら獲得するようだ。白人による不正と暴力の下に苦しみながら死んでいった数百万ものアメリカ先住民達のうち、現在もアメリカ国民に尊敬の念とともに記憶されているのは、ジェロニモ、クレージーホース、シッティングブルといった、最後まで白人と熾烈な戦いを繰り広げた偉大なる酋長達だけだ。白人の下で円満に暮らそうとワシントンDCへ赴いて「偉大なる白人の父」(*1)におとなしく服従した酋長達は、すっかり忘れ去られている。
ジョージ・オーウェルは新聞に寄せたコラムの一つで、次のように述べている。メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマといった古代文明では、現代社会が電気や化石燃料によって成り立っているのと同様、完全に奴隷制度のうえに成り立っていたにもかかわらず、おそらくスパルタカスを除いて、ただ一人の奴隷の名前も記録に残されてはいない。そして私達がスパルタカスを記憶しているのは、「……彼が『悪に手向かってはならない』という禁則(*2)に従ったからではなく、むしろ悪に対する激しい反乱を起こしたからなのだ」
************************
訳注
(*1)「偉大なる白人の父」:
“Great White Father”とは、「大統領」を意味するアメリカ先住民の表現。
(*2)『悪に手向かってはならない』:
“resist not evil”とは、聖書マタイ伝第五章からの引用。
日本語文語訳
されど我は汝らに告ぐ、悪しき者に抵抗ふな(てむかうな)。
人もし汝の右の頬をうたば、左をも向けよ
(だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向け中国支配下においては、いかなる自治状態への希望を抱くことも現実的とはいえない。なぜなら、(そうした状態を望むことは)中国の体制がその中に異なる政治・社会システムを内包できるほど柔軟で寛大であることを前提とするからだ。たとえば、インドのような国家の中にはそうした自治地域を思い描くこともできる。インドは正真正銘の多文化・多民族から成り立っており、政府の機能をはじめ、少数派や異議を唱えるグループに対する主流派の抑圧などを原則としてチェックするような憲法や自由な報道機関、自由な選挙、独立した司法制度といった、民主的な制度を備えているからだ。しかし、これらはまさにその性質上、中国指導部には実現できない事柄である。
中国指導部もまた、その国民と同様に、長く抑圧的な文化および政治遺産――一流の中国研究家であるオーストラリア人のW. J. F. ジェナーは、これを「歴史の暴君」と名付けている――の犠牲者である。それは、中国の社会や政治における前向きで抜本的な変化の実現を阻んできた。ジェナーは言う。「……中国という国家自体が監獄に囚われているという荒涼とした可能性――そこから明らかな逃げ道はなく、数千年にわたって絶え間なく強化されてきた歴史の監獄――文学的な創造物としても、そして過去の堆積した結果としても。」
香港に許されていた「一国二制度」は例外であり、北京にとって有利だったために認められたものだった。もし中国がこの制度について譲歩していなければ、当時、香港経済に寄せられていた国際的な信頼をおそらく損なっていただろうし、中国にとって大きな財政上の問題を引き起こしていただろう。共産主義へのバトンタッチに続く数年の間に、ジャーナリスト、ラジオ・パーソナリティ、政治風刺家、法律家、その他の香港における民主化を求める声は、徐々に「窒息するような」政治的風潮の中で組織的な嫌がらせや暴力的な脅し、殺害の恫喝などを受けて、その多くは香港を離れた。植民支配後の自由な中国を保証するはずだった基本法は事実上骨抜きにされ、香港島の議会および行政府は北京の支配下に買収された。
香港市民とは異なり、チベットの人々は自分達が文化的にも民族的にも言語においても、そして気質においてすら、あらゆる面で中国人とは異なっていることを激しく実感しており、骨身に沁みて知っている。チベットにおけるチベット人の暮らしが経済的に改善してきた(本質的な意味で改善しているわけではないのだが)としても、上記の点に関するチベット人の感情を著しく変えるものではなかった。ラサにおける一連のデモが、チベットの経済状況が過去と比べて著しく向上したとされる時期に起きていることを忘れてはならない。この件に関するチベット人の考え方は、1980年代後半にチベット内で出回った反体制文書からの次の引用において、最もよく表現されている。
「もし(中国の下で)チベットが成り立つなら、チベット人の生活は向上し、その暮らしぶりは幸福の度が過ぎて、三十三天の諸仏を困惑させることになるかもしれない。もし本当に、そのようなものが真に与えられるとしても、それでも我々はそれを欲しいとは思わないだろう。我々は、そんなものは要らない」なさい)。
標準英語訳
But I say unto you, That ye resist not evil:
but whosoever shall smite thee on thy right cheek,
turn to him the other also.
■ Why Give Up Now?
なぜ今、あきらめるのか?
特に中国人のチベットへの流入、とりわけ新しい鉄道の完成後にそれが加速している点を考慮すれば、チベット域内の状況が陰鬱であることはたしかに否定できない。だが、ダライ・ラマ法王の御旗を掲げる中道路線推進派による定番の議論、すなわち「中国人の流入を防ぐには、私達は自由を求める闘いを放棄して中国の支配下で生きていかなければならない」という主張は、明らかに間違っている。中国指導部や官僚の誰かが果たして、「もしチベット人が独立への要求をあきらめたら、中国人の人口移動策を考え直してもいい」などと、遠まわしにでもほのめかしたりしているだろうか? もし自由を求める闘いが放棄されてチベット域内の状況が落ち着いたら、中国人の移住は明らかに増加するだろう――過去5年間よりもはるかに大きな規模で。そして、ダライ・ラマ法王とチベット亡命政府がチベット領土における中国の統治を受け入れたら、中国人によるチベットへの人口移動が、世界の人々の目前で、完全な意味で明らかに合法化されてしまうことは、国際法に関する深い知識がなくても、容易に想像できる。
中国人の移住に対抗する唯一の策は、外国の投資家や中国人の起業家・求職者達が、「チベットは利益をもたらすどころか、ビジネスを行っていくには耐えられない土地だ」と判断せざるをえないほど、自由を求める闘いを活性化して、チベット域内の状況を流動化させることだ。たとえチベットの独立がごく近い将来に実現できないとしても、世界の耳目の前にはっきりさせておくべきことは、チベット高原は大いに「紛争中」の地域であり、チベットの独立問題は解決済みとはほど遠いという事実である。
中国人によるチベットへの移住がいかに深刻な事実であるとはいえ、この状況は完全に逆転できないわけではない、ということを、私達は肝に銘じておかなければならない。かつてスターリンは、リトアニアやラトビア、エストニアといった非ロシアの小国に対して、大規模なロシア人移住策を強行した。1939年の時点で、これら三国の人口は合計で600万人と、現在のチベット人とほぼ同数だった。スターリンは数千人ものバルト諸国の先住者達を処刑し、また数百数千の人々をシベリアに追放した。(こうした施策により、)当時の世界ではバルト三国は終焉したものと理解された。1950、60、70年代にかけては、これらの国々が存在していたことすら人類の記憶から消滅してしまったかのように思われた――これら三国の公式な代表者が、ロンドンとニューヨークに駐在事務所を構えていたにもかかわらず。リトアニアに生まれ育ったポーランド人のノーベル文学賞作家チェスワフ・ミウォシュは、自身の著作『囚われの魂』の最終章でバルト諸国の人々の声を代弁しているが、「スペインのコンキスタドール(征服者)によって絶滅させられたアステカ族のように、古代から続いてきたバルト諸国の歴史も終わりを迎えたのだ」と、心に残る痛ましい所感を残している。
しかしソビエト連邦が崩壊し、これら小さい三国は独立国家となった。諸国の中にはまだ相当数のロシア人が住んでいる。彼らはかつて三国の存続や独立性に対するあからさまな脅威と考えられていたが、もはやそうではない。心に刻んでおきたいのは、以前はソビエト全体主義とロシア移民によって完全に抹殺されたと信じられていたこれらの小さい国々が、今や自由な国家だということだ――昔から伝わる自分達の旗を掲げ、自分自身の言語を話し、自由を謳歌している。
チベットは中国支配下の最悪の時代でさえ、バルト三国ほど完全に消滅させられていた時期はない。そして今、あらゆる場所に蔓延しているビジネス上の利益や各国政府の冷笑にさらされながらも、チベットはとにもかくにも、世界の人々の関心を集め続けている。たしかにそれは、いつも私達が望んでいるような注目であるとは限らない。にもかかわらず、チベット情勢には世界中から何らかの意識が向けられており、しばしばその窮状に対して関心が寄せられている。もし、私達が独立を諦めてしまっても仕方ない、と思われるような言い訳が通じる時期があったとしたら、それは国際共産主義と中国のチベット支配が永久に続くかと思われた1960年代と70年代だったであろう。当時、自由主義世界の多くの知識層や著名人達は、共産主義中国と毛沢東首席の思想に夢中になっているように思われた。
まさに現在、チベットは、90年代の絶頂期よりは大幅に縮小したとはいえ、きわめて並はずれた注目と共感を世界中から集めている。言うまでもなく、こうした同情がチベットの大義を支える政治的な支援に転換していないのは、たしかに不運である。私達チベット人、特に宗教上の指導者は、私達の政治的な目的を世界に対して明確に、恒常的に示してくることができず無力だったことに関して、重大な責任を負うべきであろう。実際に、こうした首尾一貫性の無さが、私達自身の活動家や支援者達の間に混乱を拡大し、大義のためのあらゆる努力は泥沼に陥ってしまったのである。
■ International Dimension of Rangzen
ランゼンの国際的な局面
1990年代以降、チベット指導部と一部の西欧の支援者達は、環境や世界平和、スピリチュアリティといった「地球規模の関心事」をチベット問題と融合させようと計画してきた。こうした風潮の後、一部のチベット人やその友人達の間には、「チベット人の独立を求める奮闘は、泥臭くて限定的なもの(地球規模の姿勢ではない)」といったような、高尚で高所から見下すような、それでいてきわめて幼い発想が生じてきた。言うまでもなくこうした見解は誤りであるのみならず、人々がある種の理念の必要性を、自分達の別のニーズ――社会的受容、ポリティカル・コレクトネス、専門家としての名声や出世、そして時に物質的利益など――と混同してしまいがちであるか、その明らかな実例となっている。
自由を求める真の闘いは、局所的に(その地域で)行われているものであり、大抵は、世間体や社会的地位や経歴を失うにとどまらず、人生さえも投げうつ覚悟を備えた人々による捨て身の行為である。自由を求める闘士達はその本質上、秩序を乱す存在なのだ。けれども、いかに社会に動揺をもたらし、いかなる経済的困窮や人間にとっての苦難をもたらしかねないとはいえ、マハトマ・ガンジー、マルティン・ルーサー・キングJr、ネルソン・マンデラ、アウンサン・スーチーといった人々による不撓不屈の(そしてとりわけ局所的な)闘いは、自由を愛する世界中の人々を鼓舞してやまない――たとえば、いわゆる「世界平和」を実現するための、外交官や職業活動家、国連事務総長による善意にもとづく努力などよりも、はるかに力強く。(しかもこうした人々の言う「世界平和」の実態は、より厳密にいえば「国際社会の現状維持」と表現する方が近い。)
専制に対する一つ一つの自由の勝利は、他の大義や理念(に従事する人々)にとって、計り知れない応援となる。バングラデシュが独立を果たした時、私達はどれほど心から興奮したか、チベット人ならその感動をよく覚えているはずだ。しかも、チベット人の空挺部隊が彼らの勝利に重要な貢献を果たしたと知って、私達はさらに勇気づけられ、誇らしく感じたものだ。インドが独立した後、アフリカやアジアの各国もまた続々とヨーロッパ植民地主義から独立を果たして自由になった。1990年代にはベルリンの壁が崩壊し、今度はソビエト連邦のくびきから逃れた一連の国々が自由を獲得した。もしチベットが独立すれば、東トルキスタンや内モンゴルといった近隣地域にとってのみならず、中国それ自体の人々にとっても、自由の新しい時代をもたらしうるかもしれないし、少なくともその先駆けとなる可能性は、大いにあるのだ。
私達はまた、次の点についても留意しておかなければならない。今日の世界における最も抑圧的で残忍な政治体制――金正日の北朝鮮、軍事政権のビルマ、ロバート・ムガベのジンバブエ、イスラム・カリモフのウズベキスタン、そして、ダルフールで大量殺戮を行っているスーダン政府――が基本的に存続し続け、繁栄すらしているのは、経済・外交・そして軍事面において中国の支援を受けているからである。
■ Democracy and Rangzen
民主主義とランゼン
真に民主主義的なチベット社会においてのみ、創造性や斬新な考え方、そして新しいリーダーシップ――これこそ自由を求める闘い(Freedom Struggle)において、喉から手がでるほど必要とされているものだ――が誕生するのみならず、それらが価値あるものとして尊ばれ、効果的に機能するようになるだろう。さらに、民主主義だけが政府の機能に十分な透明性をもたらし、また私達のリーダーシップの側に正真正銘の説明責任(アカウンタビリティ)を養うことになるだろう。したがって民主主義こそが、チベットの人々のランゼンに対する真の想いが十分に表出されるための、唯一の手段となる。
抑圧されたチベットの人々にとって、民主主義は、中国の圧政からの究極の自由という目的を象徴しているだけでなく、チベット人自身の選択による真に公正で公平な政府を求めるうえで、最上の希望を示すものでもある。その意味において、真に民主的なチベットの実現を保証することは、「チベットの独立は神政的な封建主義への逆行である」と言い募る中国のプロパガンダに対して拒絶の姿勢を示すためにも、有効といえるだろう。したがって民主主義は、私達の理念にとってその潜在的な武器となり、また私達の亡命社会においてそれを純然と効果的に実施することは、自由を求める闘いに信憑性を持たせるために、疑いの余地なく必要なものとなる。亡命社会に民主主義を根付かせるための小さな一歩は踏み出されてはいるものの、より多くの事柄が実行されていかなければならない。本当の意味で党に基づいた選挙制度が、(ネパールの古いうわべだけの「パンチャヤット制(panchayat)民主主義」に似たものでしかない)現行システムに取って代わらない限り、亡命政権と亡命議会に真の民意が反映されることは決してないだろうし、独立したチベットを求める人々の望みに基づいた政策が実施されることもないだろう。
しかしながら、選挙制度の改正のみが民主的で動的な社会を確実にもたらすわけではない。チベット人が、私達の祖先がチベットに仏教を受け入れた時と同じような熱意と献身でもって、民主主義的な考え方や文化を受け入れる必要がある。時代を超えて息づいてきたチベット仏教の生命は、7世紀から13世紀にかけてインドの仏典を研究し翻訳したロツァワ(lotsawa)と呼ばれる偉大なチベット人翻訳者達の、とてつもない不朽の学問的偉業に大いに依っている。彼らの並はずれた業績は、今日に至るまでのあらゆるチベット仏教組織やその成果のすべてがそれに基づいて築かれてきたほどの、知の盤石の土台となった、といっても過言ではない。私達国家の政治的な未来の進路を導きだすうえで、チベット人は西洋民主主義と市民社会を形作った思想や哲学を研究し、議論するべきだ。私達の政治教育におけるスートラ(顕教)とタントラ(密教)には、フランスやイギリスの偉大な啓蒙の書や、アメリカや現代インドの建国の父による著述の数々、そしてそれらに続く現代の自由主義者や民主主義の旗手たちによる作品がふさわしいだろう。
そうした知的な努力、政治的な献身、そして倫理的な情熱をもってのみ、私達はチベットの独立回復をもたらしうるであろうし、法の支配および個人の自由の卓越性という理念に基づいた、政府における真の民主制度の樹立を達成できるであろう。
■ Even the Hope of Independence is Vital
独立への希望でさえも(あるいは、それこそが)不可欠だ
当然ながら、独立の日が近づいているという保証はなく、私達が生きている間には独立は達成されないかもしれない――けれども私は、いつか独立することを、ともかく確信している。いずれにせよ、ランゼンというゴールを掲げ続けることは、究極的にその獲得に至るにあたって、不可欠なことだ。困難に満ちた亡命直後の数年間、私達亡命社会を強靭に一致団結させてきたのは、ほかならぬ独立に向けた希望だったことを、忘れてはならない。私達の社会が今、直面している問題――宗教的・政治的な小競り合いや、教育水準の下降、私達の宗教の嘆かわしくも不名誉な商売化(コマーシャリゼーション)、政府におけるシニシズム、そして一般人の間の自尊心や品位の喪失など――こうした数々の問題は、チベット指導部が過去20年間、自由を求める闘いを徐々に手放してきた姿勢に、決定的な根本要因があるように思われる。
独立に向けた希望は、チベット域内の人々にとって不可欠なものである。亡命社会において自由を求める闘いを生かし続けておくことこそ、チベット域内の人々に希望を与えてきたのであり、彼らが受け続けている恐ろしい苦難にも関わらず、チベット人の文明やその世界はまったく失われてしまったわけではないという、いくばくかの保証を与えてきたのだ。チベット人が自分達自身のアイデンティティや文化や宗教を保っていくためには、自由なチベットを求める希望の灯も、常に掲げられていなければならない。もし私達が中国の一部であり続けるとしたら、私達は国家としてのアイデンティティのみならず、文化のアイデンティティをも、失うことになるだろう。北京は私達が、(ご想像の通り)「御しやすくて絶対的な、政府お仕着せの仏教徒」であることを許可するかもしれないが、中国には他にも多くの仏教の宗派やカルトが存在していることを念頭に置いておくべきだ。もし、チベット2000年の歴史を誇る不朽の文明・文化の遺産として残されてきたものが、結局は、人民共和国の山岳地域にある中国仏教の奇妙なカルト一派に過ぎない存在に陥ってしまうとしたら、それこそ究極の悲劇的なアイロニーであろう。
個人が、チベット域内においてのみならずインドの亡命社会において、あるいは異国に孤立した状態で、あるいは中国の刑務所の獄中に、たったひとりでいるとしても、その個人がはっきりと、チベット人としてあり続け、生き続けていくための唯一の道――それは、チベット独立への希望をしっかりと握り続けることであり、そして共産主義中国とそれに引き継がれてきた非人間性や悪に対する、絶え間のない果敢な抵抗を、自分自身に対して、世界に対して、示し続けることだ。
近代中国における最高の作家 魯迅(1881-1936)もおそらく、チベット人に対して、「現在の苦境に直面したまま縮こまって死になさい」などとはアドバイスしないであろうと、私は思う。魯迅は生まれつきの悲観主義者だったけれども、希望に関しては、次のような言葉を残しているのだから。
「希望は、『ある』わけでも『ない』わけでもない。希望は、田舎の小道みたいなものだ。もとは道などなかったところ――けれども、人々がいつも同じ場所を通っていくうちに、そこに道が現れるのだ」(*1)
*************
注(*1)
魯迅 『故郷』 からの一節の引用。
青空文庫には、大正期の味わい深い日本語、井上紅梅訳が公開されています。
また、魯迅ファン・おがまんさんによる、読みやすい現代語訳もぜひ。用語辞典も付いていて、素晴らしいです。
筆者プロフィール

中原 一博
NAKAHARA Kazuhiro
1952年、広島県呉市生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。建築家。大学在学中、インド北部ラダック地方のチベット様式建築を研究したことがきっかけになり、インド・ダラムサラのチベット亡命政府より建築設計を依頼される。1985年よりダラムサラ在住。これまでに手掛けた建築は、亡命政府国際関係省、TCV難民学校ホール(1,500人収容)、チベット伝統工芸センターノルブリンカといった代表作のほか、小中学校、寄宿舎、寺、ストゥーパなど多数。(写真:野田雅也撮影)